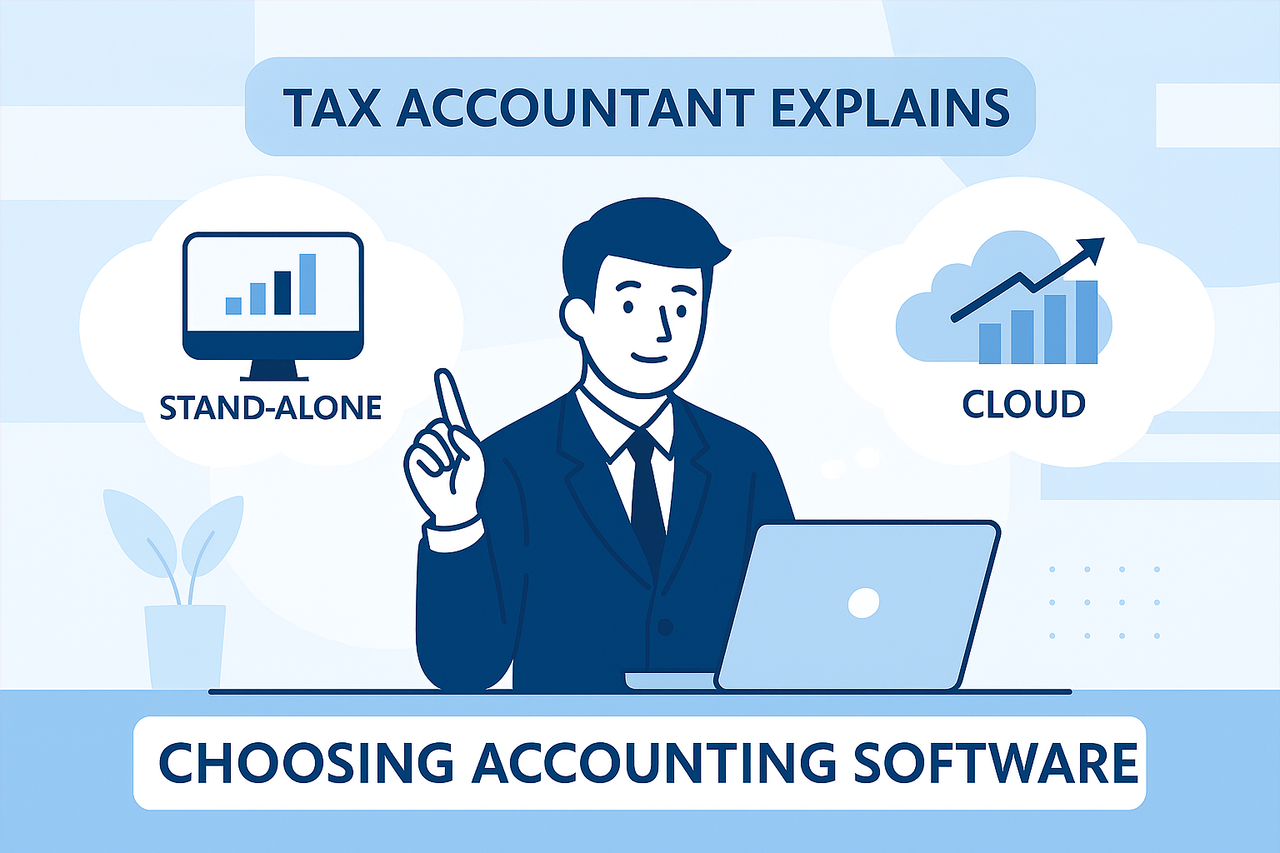〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島5丁目13-18 福島ビル422号室(福島駅から徒歩1分)
お役立ち情報
公認会計士と税理士の違いを解説|資格の役割と実務
はじめに
公認会計士と税理士。この二つの資格は日本では知名度が高い資格であり、一般にも広く認知されています。また、事業を始められ、新たに顧問を頼もうとする場合には、実際にコンタクトを取られたんじゃないかと思います。しかし世の中の多くの人は、その資格の違いをよく分かっていないかと思います。実際、私自身、公認会計士と税理士の両方の資格を持っていますが、妻もその違いを多分よく分かっていないんじゃないかなと思います。
「公認会計士は大企業向け、税理士は中小企業向け」――なんとなくそんなイメージを持っている方も多いのではないでしょうか?確かに、そういった傾向はありますが、実はそれぞれの資格には明確な役割の違いがあります。本記事では、公認会計士と税理士の違いを詳しく解説し、それぞれの資格が果たす役割や、実務上の特徴を分かりやすくお伝えします。
公認会計士とは?|監査の専門家
公認会計士の主な業務は「監査」です。「財務諸表の監査の目的は、経営者の作成した財務諸表が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについて、監査人が自ら入手した監査証拠に基づいて判断した結果を意見として表明することにある。」(監査基準1項1号https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/kijun/20201106_kansa.pdf)
この監査基準における監査の目的は、監査の勉強を始めると最初に学ぶ基本的な概念であり、まさに監査の「一丁目一番地」と言えるものです。
とはいえ、この説明だけでは少し分かりづらいかもしれません。簡単に言うと、監査とは企業が作成した財務諸表が適正かどうかを、第三者の目線でチェックすることになります。
ここで大事なのは、「適正かどうかをチェックする」といっても、公認会計士が企業に修正を強制したり、自ら手を加えて完璧なものにするわけではないという点です。あくまで、企業が作成した財務諸表を採点する立場にあり、基準を満たしているかどうかを判断するのが仕事です。
イメージとしては、試験の答案を採点するようなもので、100点満点を目指すのではなく、「80点以上なら合格」と判断するようなものです。あくまで合格ラインをクリアしているかどうかが重要です。
これは、金融商品取引法や会社法に基づく法的な業務であり、公認会計士の資格を持っていないと行うことができません。
特に、上場企業や大規模な企業では、外部の投資家や金融機関が多く関与するため、財務諸表の信頼性を確保することが重要になります。監査を通じて、企業の財務状況が適正に報告されているかどうかを確認し、投資家や取引先が安心してビジネスを行えるようにするのが公認会計士の役割です。
税理士とは?|税務の専門家
一方、税理士の主な業務は「税務申告の代理」です。法人や個人が納めるべき税金を計算し、正しく申告するサポートをするのが税理士の役割です。
税務申告は、納税者本人が行うか、税理士が代理で行うかのどちらかしか認められていません。つまり、公認会計士の資格を持っていても、税理士登録をしていないと税務申告の代理はできません。
また、税理士は税務の専門家として、税務調査対応や節税のアドバイスなど、企業や個人の税務リスクを最小限に抑えるためのサポートも行います。
両資格のイメージ
●公認会計士の仕事のイメージ
公認会計士の監査を身近な例でたとえるなら、「医者の検診」に近い存在です。企業の健康診断を行い、問題があれば早期に発見して適切な処置を助言する役割を担っています。
企業の財務状況に不正がないか、不適切な会計処理がされていないかを厳しくチェックし、必要があれば指摘・改善を促します。この監査のプロセスを経ることで、企業の財務情報の信頼性が確保され、市場全体の健全性が保たれるのです。
この業務は公認会計士にしか認められていない独占業務となります。
●税理士の仕事のイメージ
税務申告は、自分でやろうと思えばできる業務です。たとえば、「髪を切る」のと似ています。自分で切ることもできるけれど、上手に仕上げたいなら美容師にお願いするのが一番。税理士の役割も同じで、納税者自身が申告できるけれど、税理士に依頼したほうがスムーズで、リスクを抑えた適正な申告が可能になります。
税務代理も税理士にだけ認められた独占業務です。
公認会計士が税務を扱うデメリット
「公認会計士なら税務もできるのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、実はそこにはいくつかの壁があります。
- 1試験科目数の違い
公認会計士試験には税法科目も含まれていますが、税理士試験ほどの深度は求められません。特に所得税や相続税といった個人向けの税法科目については詳しくないケースが多いです。
- 2実務経験の違い
公認会計士は通常監査法人に入所し、監査業務を中心に経験を積むため、税務の実務経験がほとんどない人も少なくありません。法人税の申告書を監査業務の中でチェックする機会はあるものの、それを実際に作成することはありません。
公認会計士の強み
では、公認会計士ならではのメリットとは何でしょうか?
- 1大企業の会計・経営に精通
公認会計士は上場企業や大企業の会計を監査するため、財務管理や内部統制について深い知識を持っています。そのため、中小企業にも「お手本」となるような経営管理のアドバイスを提供することができます。
- 2分析力が高い
公認会計士は、数字をもとに企業の経営状態を分析するのが得意です。財務データのどこに問題があるのか、どの部分を改善すれば経営が良くなるのかを素早く見抜くことができます。
- 3高度な論点に対応可能
公認会計士は、企業の財務や会計に関する複雑な問題に対応する力があります。例えば、企業再編やM&A、連結決算といった高度な会計論点にも精通しており、これらの分野では強みを発揮できます。
- 4税務に精通する公認会計士も多い
公認会計士でも監査法人の経験だけでなく、税理士法人を経験している人も多数いますし、私のように税務行政に携わっていた人間も少なからずいます。そういった公認会計士は強みを最大限活かした税務サービスの提供が可能です。
公認会計士と税理士、どちらに相談すべき?
「どちらに依頼すべきかわからない」という方は、次の基準で判断すると良いでしょう。
• 税務申告・節税対策 → 税理士か、税務に精通した公認会計士
• 経営分析・会計アドバイス → 公認会計士
• 財務諸表の監査・株式上場支援 → 公認会計士
• 税務調査対応 → 税理士か、税務に精通した公認会計士
税務と会計は密接に関係しているため、両方の知識を持つ専門家に相談できるのが理想です。公認会計士と税理士のどちらに依頼するかは、目的に応じて選ぶのがベストです。
まとめ
公認会計士と税理士は、どちらも企業の経営を支える重要な専門家ですが、業務内容には大きな違いがあります。
• 公認会計士は監査のプロフェッショナルであり、企業の財務情報の信頼性を保証する役割を担う
• 税理士は税務の専門家として、税務申告の代理や節税対策をサポートする
どちらが優れているというわけではなく、それぞれ得意分野が異なります。状況に応じて、適切な専門家に相談することが重要です。
記事執筆者

岡田 健志
公認会計士・税理士
大阪国税局勤務、Big4監査法人勤務を経て2024年大阪市福島区で独立開業。JR福島駅徒歩1分の事務所を拠点に、会計・税務のプロフェッショナルとして企業の成長を支援しています 。 「数字に強い経営者になりたい」「資金繰りの相談がしたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。